掛けた鮎を取り込むときや、オトリを交換する際に欠かせない「鮎タモ」。

ただし、各メーカーからさまざまな製品が販売されており、はじめて購入する際にどれを選んだらよいのか、迷ってしまう方もいるのではないでしょうか?
そこで本記事では、選ぶ際に押さえておきたい以下のポイントを解説します。
 編集長コウジ
編集長コウジあわせて、おすすめの鮎タモをご紹介するので、購入を検討している方は参考にしてみてください。
ポッドキャスト風の記事解説
「鮎タモ」とは


鮎タモは掛かった鮎を取り込む際はもちろん、オトリを交換するときにも使用する鮎釣りの必需品です。
「鮎ダモ」「玉網」とも呼ばれています。
他のジャンルでは釣り網のことを「ランディングネット」と呼ぶ場合がありますが、鮎釣りでは馴染みません。
「タモ」や「鮎ダモ」と呼びましょう。
「鮎タモ」の選び方3つのポイント


鮎タモを選ぶ際に押さえておきたいポイントは、以下の3つです。
では、それぞれ詳しく解説していきましょう。
タイプをチェック
鮎タモには大きく分けて、以下3つのタイプがあります。
- 一般的なスタンダードタイプ
- 袋タモ
- 返し抜き用タモ
「網なんてなんでもいいじゃないか?」と思うかもしれませんが、それぞれ向き不向きがあるのでチェックしておきましょう。
一般的なタモ


袋のない、もっともスタンダードなタイプです。
大きさには、おもに36cmと39cmの2種類があります。
一般的なのが39cmです。
腰以上に立ち込むシーンでは小さいほうが水流抵抗が小さく使いやすいですが、小さいほど取り込みでキャッチしにくくなります。
初心者においては、39cmを選んでおくのが妥当です。
袋タモ


底部にナイロン生地の袋を装着しているタイプが「袋タモ」です。
袋に水を貯められるので、鮎を入れたまま小移動したいときに活躍します。
袋のないタモは引き舟にオトリを仕舞わないとポイントを移動できないですが、袋タモなら貯めた水にオトリを浸けながら移動可能。
ちょっと移動するたびにハナカンを外してオトリを引き舟に入れ、再び取り出してハナカンをつける、といった一連の作業を省けるわけです。
とくに、小河川や上流域で引き舟を腰から外して釣るようなシチュエーションで活躍。
引き舟を浸けた位置から離れてしまっても、袋ダモならオトリと掛けた鮎を弱らせずに引き舟のある場所まで戻れます。
ただし、流れに浸けた状態では水流抵抗が強くかかるため、大河川で腰ほどまで立ちこむスタイルには不向きです。
返し抜き用


「返し抜き1」で取り込むのに適した鮎タモです。
サイズが小さめで水流抵抗を受けにくく、枠部分に返しをつけて鮎が逃げにくい工夫を施したモデルもあります。
ただしサイズが30cm以下と小さく、飛ばした掛かり鮎を直接タモで受ける通常
「引き抜き」には向いていないほか、種類が少なく選びにくいです。
網目の大きさで選ぶ
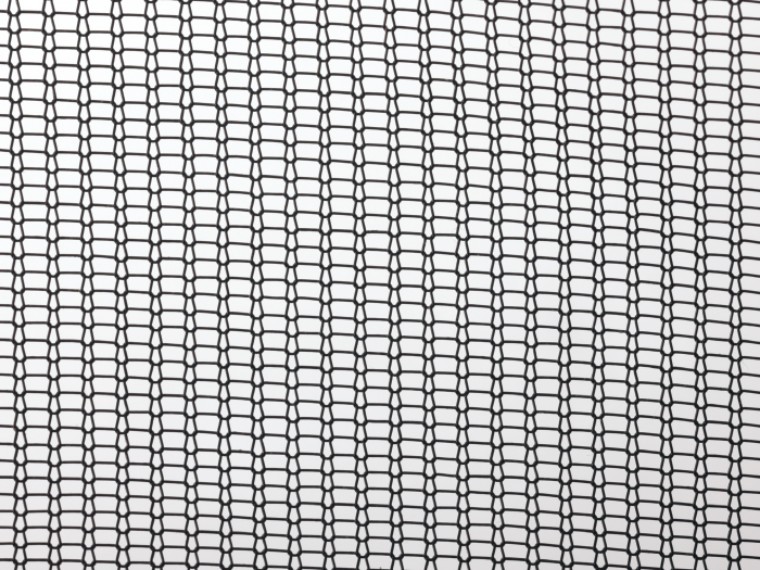
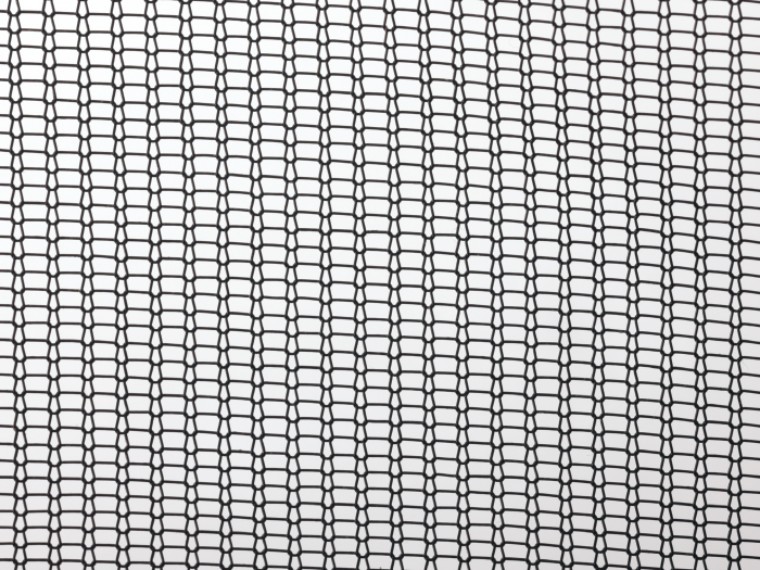
鮎タモはモデルによって、およそ1~5mmと網目の細かさが異なります。
小さい網目になるほどハリやハナカンが引っかかりにくく、ストレスのなく鮎釣りを楽しめるのが特徴。
また、鮎のヌメリが取れにくくオトリを弱らせにくい点もメリットです。
ただし、網目が小さいほど水流抵抗が大きくなります。
とくに、荒瀬に腰まで立ち込む際には、タモにかかる水流抵抗が負担になりやすいので注意しましょう。
荒瀬用として購入するなら、4~5mmほどの粗目タイプが目安です。
初心者がはじめて購入する1本なら、価格と使いやすさを考慮するのが重要。
網目が小さいほど製造に手間がかかり、高価格な傾向があります。
リーズナブルなタモを探すなら、1.5~2mmほどから手頃なモデルを選ぶのがオススメです。
機能性で選ぶ
鮎タモのなかには、使い勝手のよい機能性に優れたモデルが各メーカーから販売されています。
腰に差しやすいようグリップ形状を採用したり、底部に角度をつけて魚が動き回らない工夫をこらしたりといったタイプも。
着脱式グリップでコンパクトに収納できるタイプは、荷物をなるべく小さくまとめたい場合に役立ちます。
ただし、工夫をこらしている鮎タモは高価格な傾向があるので、予算と必要性のバランスを考慮して選びましょう。
鮎タモを使った取り込みシーン
「鮎タモ」のタイプ別おすすめ製品
鮎タモの選び方を理解したところで、オススメモデルを見ていきましょう。
以下の2タイプに分けて紹介します。
スタンダードタイプ
シマノ(SHIMANO) 鮎ゲーム タモ PD-1C3X
手軽に鮎釣りを楽しむをコンセプトに登場した鮎GAMEシリーズの鮎タモです。
39cm枠に1.5mmの機械編を採用し、スタンダードなモデルを探している人にオススメ。
上位グレード「リミテッドプロ」譲りの機構を採用し、基本性能に優れています。
シマノ(SHIMANO) 鮎ダモ LIMITED PRO PD-1C1V
網の取り付け構造を見直した鮎タモです。
ワイヤーが切れてもすぐには網が抜けにくい構造になっているのが特徴。
また、ジョイント部分のアルミ削り出しで剛性も向上しています。
グリップに穴を開けて、立ちこんだときに水流抵抗を軽減させているのもオススメポイント。
枠付近に膨らんだ形状の「鮎返し」を設けており、鮎が飛び出してしまうを防いでいます。
シマノ(SHIMANO) 鮎ダモBASIS PD-1C2V
基本星に優れているスタンダードな鮎タモです。
グリップに穴をあけた構造により、立ち込んだ際の水流抵抗を抑えられるのが特徴。
枠付近に膨らみを設けており、のぼってきた鮎が飛び出してしまうのを防げるのもオススメポイントです。
シマノ(SHIMANO) 鮎ダモZ PD-1G1V
必要十分な機能を搭載した鮎タモです。
スタンダードなタイプで手頃な価格もモデルを探している人にオススメ。
初心者にも使いやすいエントリーモデルです。
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモMS3915
オール約1.5mm網目の鮎タモです。
結び目のない滑りのよさで魚体を傷めにくい、機械編みでつくられています。
ポリエステルの採用で張りがあり、網の形状がくずれにくいのが特徴。
抜き差しのしやすいグリップ形状を採用しているほか、持ち運びや保管に便利なキャリーケースが付属しています。
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモSF競技SP3910速攻
オトリを素早くつかめて手返しの速い釣りを展開できる「スピードフォルム形状」を採用している鮎タモです。
トーナメントの限られた時間内に1匹でも多く掛けたい、エキスパートにオススメ。
従来モデルよりフレームが肉厚になっており、ネジレや曲がりに強い耐久性が魅力です。
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモMS競技SP3910
一般的な丸型形状の網を搭載した鮎タモです。
網目は底部1mm・側面1.5mmで、仕掛けが網に絡むトラブルを減らせます。
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモSF競技3915速攻
スピードフォルムをさらに進化させた、速攻タイプの鮎タモです。
掛かり鮎をつかみやすく、オトリをスピーディーにポイントへ送り込めます。
手返し重視のトーナメンターにオススメです。
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモV
枠系36cmのフラットフレーム採用のシンプルな鮎タモです。
買い求めやすい価格で、初心者のはじめての1本としてオススメ。
仕付け糸がない仕様で、糸にやさしいフラットフレーム構造を採用しているのもポイントです。
網には、型くずれしづらい2mm目ナイロンマルチフィラメント網を使用。
尻手ロープ取り付け穴を設けているほか、専用ケース付属で持ち運びや保管に便利です。
がまかつ(Gamakatsu) がま鮎受けダモ GM-9953
バランス設計を追求している鮎タモです。
網部には、テクノメッシュを採用しています。
エクセル(X’SELL) レース網 鮎手玉 1.0mm(36cm枠) FP-298
リーズナブルなエントリーモデルの鮎タモ。
レース生地で張りがあって、型崩れしにくい約1.0mm目ポリエステル網を採用しています。
安価ながら、保管に便利なケースが付属しているのもおすすめポイントです。
エクセル(X’SELL) 鮎タモFPメッシュ FP-307
1.5mmの機械編みの網を採用している鮎タモ。
結び目がなく、イカリ針やハナカンの引っ掛かりにくいのがおすすめポイントです。
網の表面が平滑で、鮎のぬめりが取れにくい点にも注目。
水切れの良い素材により、川に立ちこむ際の水の抵抗を減らせます。
エクセル(X’SELL) レース網鮎手玉 1mm 39cm FP-302
39cmのスタンダードな鮎タモです。
編み目1mmで、仕掛けや針が引っかかるのを防げます。
買い求めやすい低価格が魅力です。
袋タモ
ダイワ(DAIWA) 鮎ダモV39F
型崩れしにくい2mmナイロン袋を採用した袋タモです。
水を入れても型崩れしにくいほか、網と袋の繋ぎ目にイカリ針が引っ掛かりにくいフラットな縫製構造が特徴。
また、仕付け糸がなくラインに優しいフラットフレーム構造を採用しています。
専用ケースが付属しており、保管に便利です。
シマノ(SHIMANO) 鮎袋ダモZ PD-1H1V
39cmの袋タモです。
バランスに優れたグリップには穴を設けてあり、水流抵抗を減らせます。
がまかつ(Gamakatsu) がま鮎 袋タモ GM9951 36cm
機動力を重視したい方におすすめの36cmの袋タモです。
ジョイント部に尻手ロープ取り付けフックを設けているほか、コインで着脱できるジョイント部を採用しています。
エクセル(X’SELL) レース網鮎袋タモ 1.0mm FP-300
36cmの鮎タモです。
網目1mmで仕掛けや針が引っかかるの防げます。
買い求めやすい低価格も魅力です。
鮎タモを守る「尻手ロープ」も用意しておこう
「尻手ロープ」とは、タモを腰の鮎ベルトと接続するためのロープです。
大切な鮎タモを流してしまうトラブルを防げます。
とくに、腰まで立ち込む際に尻手ロープを使用しないで鮎ベルトに差しておくのは危険。
気づいたときには「腰にあったはずのタモがない!」、という事態が起こりえます。
また、流されたのに気づいて、強い流れのなかを必死に追いかけると水難事故になる恐れも。
基本的に、鮎タモには尻手ロープを接続する穴を設けています。
鮎タモとセットで、尻手ロープも購入しておくのがオススメです。
鮎タモに関するよくある質問
- はじめて購入するなら、どんなタイプがおすすめ?
-
スタンダードな39cmタイプの鮎タモがおすすめです。
編み目は、1~2mmなら針の引っ掛かりが少なく快適に使えます。
- 鮎タモはいくつ用意おくと良いですか?
-
基本的にひとつ用意しておけば十分です。
スタンダードな鮎タモがあるなら、小河川用に袋ダモがあったら便利と思えば購入して使い分けると良いでしょう。
ただし、流失したら釣りを続けるのが難しくなるので、尻手ロープを必ず装着してください。
- 網が破れたら交換はできますか?
-
できますが、慣れていない方が自分で交換するのは難易度が高いです。
また、高品質な鮎タモのネットは入手できたとしても価格が高く、長く使っているなら寿命と考えて買い替えを検討しましょう。
- 鮎釣り用以外のランディングネットではダメですか?
-
腰の鮎ベルトに挿して使える大きさなら使用はできますが、おすすめはしません。
鮎タモは引き抜いた際にキャッチしやすい大きさ、針が網に引っ掛かりにくい編み目の細かさなど、鮎釣りに特化しています。
予算の関係でどうしても他のネットを流用したい場合は仕方ないですが、できれば鮎釣り専用の鮎タモを用意しましょう。
- 鮎タモがないと釣りができませんか?
-
鮎タモを持って行くのを忘れた場合、鮎タモがなくても釣り自体は可能です。
ただし、取り込みやオトリの交換などを鮎タモなしで行うのは初心者には難しいと思います。
ベテランなら最悪鮎タモなしでも対応できますが、基本的に必需品と考えて差し支えありません。
お気に入りの「鮎タモ」を見つけよう!
鮎釣りで必要不可欠な鮎タモ。
袋ありとなしがあるので、はじめて購入するなら通う予定の川に合わせて選ぶとよいでしょう。
できれば川の規模やポイントに合わせて、使い分けできるのがベストです。
今回の記事を参考に、お気に入りの鮎タモを見つけてみてくださいね。
記事中で出てきた専門用語
- 返し抜き:掛かり鮎を上流に飛ばして、流れてきたところを吊るし上げて取り込む方法 ↩︎





















